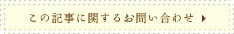令和6年度地域連携型学生研究公開審査会開催
2月17日、熊本県立大学で「地域連携型学生研究公開審査会」が開催されました。地域連携型学生研究とは、地域社会・地域企業から共同研究のテーマを募集し、そのテーマに対し、学生研究として取り組むことで、実社会と学生とを結びつけ、学生の自律と自立に向けた就業力の育成、向上を図るものです。本制度は、平成23年度から始まり令和6年度で14年目を迎え、今年度は11のグループが様々な団体と連携し、宇城市地域振興課も佐藤研究室と「空き家所有者への効果的な意識改革に関する研究」というテーマで1年間研究に取り組んできました。
※詳しくはこちらをご確認ください。熊本県立大学地域連携型学生研究ホームページ(外部リンク)
公開審査会では、11のグループが1グループ当たり7分間で発表を行い、教員による評価から「最優秀賞」と「優秀賞」を、学生による相互評価から「学生賞」が授与されます。佐藤研究室は、代表で4年生の杉本陽菜(すぎもとひな)さん高畑莉央(たかはたりお)さんの2名が1年間に行った研究の内容と成果について発表を行いました。
発表の様子。右から杉本さん、高畑さん。
研究の内容としては、宇城市空き家バンクで成約した物件の空き家バンクホームページでのアクセス数や掲載日数についての分析と新たな空き家の評価基準の導入により、成約する要因を明らかにし、成約可能性予測指標を作成しました。また、成約者へのアンケートやヒアリング調査を実施し、空き家の成約に繋がる効果的な改修方法について研究しました。改修のイメージをわかりやすくするため、パーツを付け替えて改修を体験できる模型を製作。加えて、いえの手帳簡易版を新たに作成し、登記や空き家に対する新たな法律の説明、空き家を放置した際にかかる費用等を掲載しました。研究の一環として、松橋町8区でワークショップを開催し、改修模型やいえの手帳簡易版についての評価をいただきました。
※ワークショップの様子はこちらをご確認ください。熊本県立大学生と空き家啓発ワークショップを開催
発表のスクリーンの様子。
全11グループの発表終了後、教員と学生による評価の時間があり、審査結果の発表がありました。残念ながら、賞を取ることはできませんでしたが、研究の内容と成果については、今後の空き家バンクの運用や空き家対策に繋がるものになりました。今回の研究で作成した「成約可能性予測指標」は、令和7年度から実際に活用し、効果検証を進める予定です。また、改修模型については、地域振興課の窓口に常設していますが、3月29日開催の「空き家イベント@不知火美術館」でも展示しますので、是非改修の疑似体験にお越しください。
改修模型の写真。
今後も佐藤研究室とは連携を図りながら、一人でも多くの人に空き家について関心を持ってもらい、空き家の解消に繋がるよう対策を進めていきたいと思います。
佐藤研修室の皆さん。前列、右から杉本さん、高畑さん。後列、右から佐藤准教授、森さん、廣田さん。
追加情報
追加情報:外部リンク
このページには、外部リンクが含まれています。